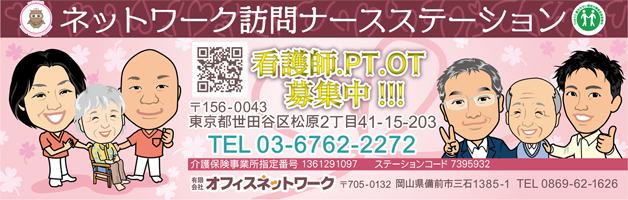T様 90歳代 男性 要介護5 お泊りデイ利用中 現病歴:閉塞性腎機能障害・認知症・高血圧
お泊りデイを利用しながら、月に1~2回、日中に自宅へ戻り家族との時間を過ごしていた。
発熱や高血圧、全身浮腫が出現したため総合病院へ救急搬送。閉塞性腎機能障害と診断される。
数週間の入院治療を受け、膀胱留置カテーテルは永久留置となり退院。退院後はお泊りデイを利用しながら、定期的な訪問診療と訪問看護のサービス開始となる。
今後は特養老人ホーム入居予定。お泊りデイサービスでは、日中車椅子に座り食事やレクリエーションに参加。
穏やかな性格だが認知症があり、膀胱留置カテーテルを弄り、固定位置などの工夫が必要だった。
またカテーテル内の浮遊物や混濁、尿道口からの出血等のトラブルがあり、頻回なカテーテル交換が必要だった。
突然、臀部と左大転子部の表皮剥離が出現。主治医の指示のもと、デュオアクティブ貼付開始。
頻回の処置は行ったが、創部は徐々に悪化、新たに右大転子部にも発赤が出現。
使用していたリクライニング車椅子による姿勢の崩れや摩擦が褥瘡へ影響していると考えられた為、車椅子の変更したり、ご本人の様子や褥瘡の変化を適宜モニタリング実施。
褥瘡は更に悪化しため、頻回な処置が必要で自宅療養開始。自宅に介護ベッドとエアマットへ変更を行う。
連日訪問し、褥瘡処置と共に全身の清潔ケアを徹底したことで全身の浮腫みや乾燥が改善し、血尿や尿混濁などの尿道カテーテルのトラブルが無くなった。
臀部と左大転子部の褥瘡は徐々に改善していったが、黒色壊死組織やポケット形成がみられ浸出液は悪臭を放った。
壊死組織は徐々に剥がれ筋腱組織が露出し、肉芽形成を期待し処置を継続したが改善に乏しかった。褥瘡は悪化し、血性膿瘍の浸出液が多量に出るようになっていった。
経口摂取量は減少し、るい痩著明。活気減退し微熱を伴うようになり、1~2週間後に意識レベル低下で、救急搬送、電解質異常と炎症反応高値を認め入院加療となった。
褥瘡の治療は深達度によって治療過程が異なるため、創の状態を正しく評価し適した外用薬の選択と全身状態、栄養状態も併せて看ていく必要がある。
褥瘡発生時から、悪化リスクも視野に関わっていた。
治療に重きを置くと自宅療養や入院にて集中的に治療していくことが望ましいと考えていたが、T様とご家族様それぞれに生活がある。
入院するか自宅療養するかの判断一つが大きく影響を及ぼす可能性があるため慎重な判断が必要だと感じた。
また治療経過が思わしくなく、看護師がもっとこうしてみてはどうだろうと思っていても医師の判断が異なる場合があった。
もやもやした気持ちのまま行うケアは心苦しい場面もあったが、事務所内のスタッフと情報を共有することで違った考えを知ることができ、どう工夫すれば良い看護の提供ができるか考えるきっかけとなった。