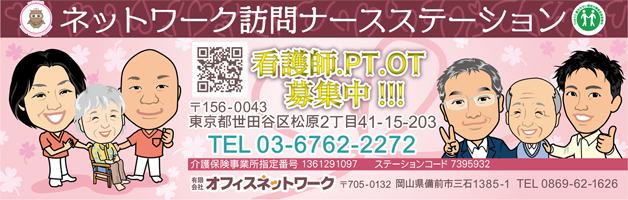K様90歳代 女性 要介護2 娘と同居しているが日中は独居 現病歴:重症大動脈弁狭窄症、高血圧症、腰痛症。
夫の介護困難で地域包括支援センターに相談、夫(没)の看護介入で、K様にも看護師介入が必要と提案し訪問開始。
介入当初は通院歴や既往歴がなく、訪問診療開始で大動脈弁狭窄症は重症であった。ご本人は手術は希望せず保存治療、最期の住処は自宅希望。
身丈よりも高く積まれた段ボールや衣服、ビニール袋にまとめられた書類や食べ物、使用済みのオムツ、歩行できる幅は人が一人通れる程度。
汚れたものも袋にしまって「後でやろうと思った。」と良い、長年にわたり物をため込み不衛生な自宅環境であった。
片付けたい気持ちはあり、身の回りの物の整理を始めるが逆に散らかっていく一方。数年前のチラシ一つ捨てる選択をしない。
看護師が片付ける素振りを見せたり少しでも環境が変わったりすると「調子が狂う。」と言い苛立つ。
ベッドを置くスペースなく、1日中ソファで過ごし、手の届く範囲に娘様が用意した食事や飲み物、薬、衣服、オムツ、在宅酸素など設置している。
テレビを見たり、ソファの上に足を挙げて横になってみたり、身の回りの物を袋詰めしたりして過ごしている。
唯一大便はトイレに歩行するが、亀背や筋力低下、心負荷が増大傾向にあるため息切れが出現、労作に伴うSPO2低下があり歩行後の疲労感が強く、自覚あり。
自ら失禁しリハビリパンツを重ね履きし、複数の尿取りパッドをしているが、尿汚染みられ自宅内は尿臭が染みついている。
母娘との折り合いの悪さや住環境の悪さやセルフケア不足で、娘様は施設入所させたいというが、全く探すことはない。
K様は自宅で生活したいと主張しているが、娘様に強制的にショートスティに入れられている。自宅での生活を継続するには環境整備の必要があった。
これまで幾度となく整理整頓を行ったが、すぐに元の環境に戻った。
排泄物汚染の頻度が多くなった頃にポータブルトイレの設置案を提案すると「それ、良いわね。」と前向きであった。
娘様にも説明し同意が得られたため、ポータブルトイレ導入の準備をしていた。
しかし場所の確保や排泄物の片づけは誰がするのか、便の臭いは大丈夫なのか等の理由により娘様より断られ実現には至らなかった。
またヘルパーの導入が検討されるが娘様が自宅に人を入れることを拒んだ。K様は自宅生活継続のための提案は積極的であったが、娘様の真意はわからず、なかなか纏らず前進できていない。
以前よりも筋力低下や呼吸困難感が増大し「一人で生活するのが難しくなているね。」「誰かが居てくれると良いのだけど、一人じゃトイレまで歩くのは怖いね。」の発言する。
素直にショートスティに行ったり、、娘様による排泄介助や着替えなども受け入れるようになっている。
「ここに住みたければ頑張らねば。」と自分を鼓舞する姿もあり、大胆な整理整頓や環境変化は受け入れ難いため、身の回りや歩くためのスペース、安全確保など、支援者の考えを押し付けず、限られた条件の中で、その人や家族を受け入れる事の大切さを学んだ。