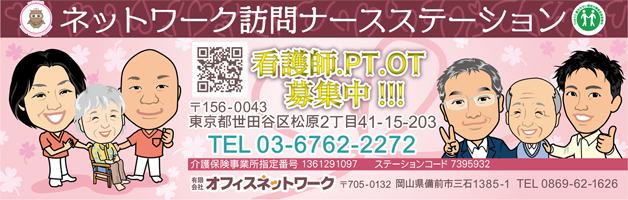K様70代後半、男性。要支援2、生活保護受給。 現病歴:高血圧で近隣クリニックで降圧薬や目薬処方。
既往歴は不明で、精神疾患の診断はないが、若い頃より吃音的で声が小さくコミュニケーションを取るには時間を要す。
出身は関東で両親は他界、兄弟や結婚歴もなく九州に遠い親族がいるが音信不通。 唯一の友人(男性)が近隣に住んでおり週に1~2回は遊びに出かけている。
賃貸2Kアパートに居住、買い物や外出、部屋の掃除等も自分で出来ていたが、最近になり出先の屋外で転倒することが多くなり、地域包括支援センター経由で訪問看護の導入に至る。
担当者会議にて訪問看護週1回、訪問介護週2回(シャワー浴介助・室内清掃等)、福祉用貸与(タッチアップ)、シャワーチェアー購入。
サービス自体に拒否はなく、気が向くと、自ら近隣へ買い物に出かけたり、バスに乗車して通院も出来ていた。
サービスも安定してきた頃『最近飲み込みがスムーズにいかない』と訴えるようになり、かかりつけ医に受診相談するように伝える。
クリニックでは検査不可で総合病院の紹介状を持って、数日後、総合病院を受診。当時はコロナ禍で、検査はかなり先になると説明を受けた。
訪問時に傾聴すると、本人は総合病院で入院し治療出来るものと思っていたので、ショックを受けていた。
コロナ禍で軽症の患者さんはなかなか入院出来ないと説明しその日は退室する。
翌日になり友人宅に遊びに行ってる最中に嘔気があり、夜中に救急車要請するも救急隊が症状が軽症の為、搬送せず。
ヘルパーさんから情報が入り、緊急訪問するも「俺はどうなってもいい」と投げやりな発言があった。
バイタルサインや急を要する症状もなくクリニックに報告のみ。
翌日ステーションに警察署から電話が入り、「K様と思われる方が昨夜〇〇埠頭で水死体で発見されたが、本人確認出来ないので確認して欲しい」との内容であった。
ご本人を確認し、1月の極寒な海での投身なのか転落なのか不明ではあったが、埠頭まで行った心情を想像するだけで眩暈がしショックでした。
ステーション内でも振り返りを行い検証しました、チームとして訪問看護師として、利用者の心の変化に気付く看護や未然に防げなかったものかと思案しました。
K様の中ではどの段階で決心に至ったのか本人でなければ分からない部分ではありますが、今でも自分たちの力不足を感じ、悔いの残る事例です。
失敗ではなく、次への学びの機会として、K様が身を挺して教えてくださったことを真摯に受け止め、これからの看護・チームでの役割等の再構築や自己研鑽を積み重ねていく所存です。