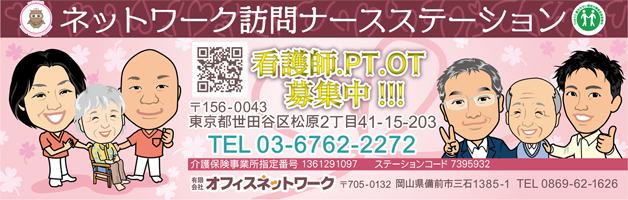A様60歳、女性。要介護5、夫と子ども2人と生活。 現病歴:若年性認知症(前頭側頭葉型認知症)、既往歴は無し。
3年前より物忘れが多く行動異常の出現、衝動性障害・徘徊あり、自発言語は少なくなりADL低下、失禁もみられ日常生活のサポートとして介入。夫と成長期の子ども2人と平穏な生活を送っていた。
2021年12月頃、物忘れが増え日常生活に支障をきたし、病院受診すると、前頭側頭葉型認知症と診断される。
病院の主治医の勧めで訪問看護週2回、入浴介助・医療相談ケアで介入した。コロナ禍もあり、夫は自宅ワークに切り替え、介護を行った。
A様と思春期の2人の子どもの世話を一人で背負うこととなる。A様の食事、排泄、入浴を夫が介護。
日中はリビングのソファーで一緒に過ごし、夜はソファーベッドで共に寝る生活だった。
物忘れ・徘徊・転倒などあったが、一部介助での自力歩行、食事摂取、刺激での発語があり、入浴も湯船につかることもできた。
週末はデイサービスを利用し、夫の束の間の休息の時間も確保できていた。
症状の進行は想像以上に早く、今年の5月頃には、これまで出来ていた歩行ができなくなり、発語は全くなくなった。
食に意識がいかず食事介助するも飲込み難で、すぐ咽込むようになる。生活全般に介助が必要で、介護負担が大きくなった。
夫の希望で、摘便と入浴を看護師2人体制で抱きかかえて介助する状態だった。
食事摂取量が減り体重減少、るい痩著明で、栄養状態が悪くなったA様の臀部には褥瘡発生し、日ごとに皮膚が壊死していく状態だった。
発語がなく意思疎通が難しくなると、自信のあった夫の介護は孤独を生み、A様に声を荒げるようになった。
「(妻が)何も返事しないから、言うこと聞かないからどうしていいのかわからない」と漏らす夫に、介護方法や処置方法を指導するも、できない・難しいと返事で、更に追い込んでしまう状況になってしまった。
「昨日までは一口食べれたんです」と誤嚥し吸引を強いられ、変わりゆく妻の姿に混乱した様子だった。
いずれは施設入所と考えていたが、まだ先の事と手続きや金銭的な事など全く進んでいなかった。
以前から訪問診療を勧めていたが、急に通院できなくなり、A様が生死の淵に立たされたとき、現状を受け止めSOSを出した。
子ども達にもA様の予後を話すタイミングにもなった。訪問診療が介入してすぐ様態急変し、高熱を出し救急搬送となり、加療入院となった。
入院中に病院のワーカーさんの協力で、療養型病院に転医する段取りができた。
看護師として急激に進行する病気に対して、夫や家族の理解と社会資源活用に繋げるために、どのタイミングで寄り添いサポートすればよかったのか、
また、一人で抱える介護・子育ての負担、精神的負担が限界になる前に、レスパイトケアをどのように行えばよかったのか、とても考えさせられた看護でした。